長勝寺の文化財
長勝寺の文化財
木造伝池田八幡本地仏座像 【国指定重要文化財(彫刻)】

この像は、亀山八幡宮の神体として祭られていましたが、明治の神仏分離政策により、長勝寺に移されたものです。
首から上は仏様、下は神様の姿をしている「本地仏」は三尊からなり、いずれも檜の一本造りです。平安時代から信じられていた、仏が人々を救うために神の姿で現れるという「本地垂迹説(ほんじすいじゃくせつ)」を具現化した全国的にも珍しい作例であるため、国の重要文化財に指定されています。
| 時代 | 平安時代後期 |
| 指定 | 大正8年8月8日 |

菩薩形

如来形

僧形
梵鐘【国指定重要文化財(工芸品)】

この鐘は銅製で総高84.5センチメートル、口径48.3センチメートルで鐘身は縦帯で4区、横線で3間に分かれ、建治元年(1275)の刻印があり、作者・勧進者・製作者が明示されています。
作者については、河内国舟那郡黒山郷下村(現在の大阪府堺市美原区)の平久未が製作したことが刻まれており、また鋳造場所も美原区の真福寺遺跡で鋳造されたと推定されており、河内鋳物師の活動であったことがうかがえます。
もともと西の滝の龍水寺のものでしたが、同寺が早くに無住となったため、兼帯していた長勝寺の収蔵庫に収められています。
| 時代 | 鎌倉時代(建治元年) |
| 指定 | 昭和41年6月11日 |


宝篋印塔【国認定重要美術品】

西の滝の龍水寺本堂にある洞穴の中に安置された高さ1.2メートル余の石塔で、建武5年(1338)に建立され隅飾突起、反花座、各狭間ともに南北朝の様式(関西型)の特徴をよく表しています。
昭和18年10月1日、国の重要美術品として認定され、いまは木造伝池田八幡本地仏座像、梵鐘とともに長勝寺の文化収蔵庫に収められています。
| 時代 | 南北朝時代(建武5年) |
| 認定 | 昭和18年10月1日 |
- 「重要美術品」は、「重要美術品等の保存に関する法律」(昭和8年)によって規定されるもので、「文化財保護法」(昭和25年)の制定により廃止されましたが、同法により現在もなお効力を有するものと規定されています。
| 所在地 | 長勝寺(小豆島町池田) |
| 見学 | 詳細は、長勝寺(0879-75-0343)までお尋ねください。 |
この記事に関するお問い合わせ先
生涯学習課
〒761-4492
香川県小豆郡小豆島町片城甲44番地95
電話番号:0879-82-7015
ファックス番号:0879-82-1025









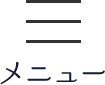



更新日:2021年08月18日